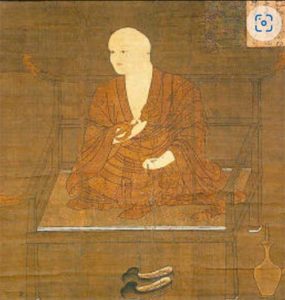『海辺の光景』『アメリカ感情旅行』『流離譚』安岡章太郎(1920~2013)
連載・文学でたどる日本の近現代(42)
在米文芸評論家 伊藤武司

第三の新人
戦後、第三の新人と呼ばれた安岡章太郎は大変ユニークな人生を歩んだ。第一次・第二次の新人がヨーロッパ風の長編小説を目指したのに対して、安岡や吉行淳之介、遠藤周作は、戦前の主流だった私小説・短編小説への回帰をはかったのが特色とされる。
1920年、高知市に生まれた安岡は、陸軍獣医の父親と共に軍隊の拠点を移り住む。5歳で朝鮮の小学校に入り、9歳で青森県の弘前の学校に転校し、10歳で東京の世田谷へ移る。旧制第一東京市立中学校(現:千代田区立九段中等教育学校)に入学したのが13歳だった。成績も素行も悪く、寺に預けられ、高校受験にも失敗、落ちこぼれの青春である。
3年の浪人生活を経て慶応大学予科に入学すると、下町に下宿。授業をずるけ、仲間らとコーヒー店に入りびたりながら、江戸末期の戯作作家を気取り、荷風のようになろうと創作を始めた。太平洋戦争で陸軍に応召、満州の歩兵連隊に派遣されたが、肺疾患のため除隊。重度の脊椎カリエスで闘病生活のなか終戦を迎え、28歳で大学を卒業したのが昭和23年。不運の連続は太宰治をほうふつとさせるが、安岡の不屈の精神は失せなかった。
雌伏10余年を経て昭和26年、短編『ガラスの靴』を「三田文学」に発表。次作『宿題』と連続して芥川賞候補に選ばれ文壇デビュー。『ガラスの靴』から『海辺の光景』までの作品を基に、平野謙は「もしかりに安岡章太郎が劣弱者意識だけの作家だとしたら…小粒な作家に終わったろう」とし、「自己を転換させ得た」と洞察。「いつか、『海辺の光景』にまさるとも劣らぬ秀作を、私どもに見せてくれることだろう」との予感は的中する。一時期の停滞はあったものの、33歳の時の『悪い仲間』『陰気な愉しみ』で芥川賞を受賞、47歳での『幕が下りてから』が讀賣文学賞を、『走れトマホーク』『私説聊斎志異』を経て、71歳で『伯父の墓地』が川端康成文学賞を、80歳で『鏡川』が大佛次郎賞を受賞し、教科書にも採用された。文芸評論から作家論、エッセイ、旅行記、対談を発表し、最大の傑作が長篇歴史小説『流離譚』である。
デビュー作を一読した北原武夫は「日本文壇の新精神」だとし、村上春樹は「文章にキレがあり、実に生き生きしている」と評価している。
芥川賞の『悪い仲間』は、不良仲間3人の身辺をユーモア、ギャグ、自己嫌悪、思い上がり、羨望、自傷の念などを表現したドタバタ青春物語。『陰気な愉しみ』は、終戦後、横浜の役所へ障害者手当をもらいに行く「僕」の話。ギプスを付けたあわれな姿の屈辱感、気まずさや恐れ、自己嫌悪を描き、金を手にすると高揚した気分でショーウインドウを覗いたり、自慢顔で食べ物を買う屈折した心理をとらえ、陰気な愉しみに喘ぐダメ人間をみごとに素描した。これらを「何もすることがないまま、ふとんの中にもぐりこんでムカシのことをあれこれ想い出しているうちに、何となく出来上がったものだ」と『私小説の不可能性』で明かし、こうした言葉がサラッと口に出るのが安岡らしい。
選考では『悪い仲間』を丹羽文雄が支持し、佐藤春夫は「新進にはちと過ぎた風格」のある結びだと褒めている。やがて安岡は第三の新人のリーダー的存在となり、文芸評論家の奥野健男は、グループの「看板」だったと言う。
一見異質と思われる阿川弘之と安岡は同年生まれで親交があり、阿川は『志賀直哉』、安岡は『志賀直哉私論』を書くという共通項もあった。
短編の名手
50代からの安岡は短編の名手を自認して私小説的創作に健筆を振るうが、『贅沢な文学』では、「短編文学が作品論そのものの対象にならない」と嘆き、「短編小説は贅沢な時代の贅沢な文学」であると自虐とも皮肉ともとれる言葉をはいていた。
安岡くらい自己を語る作家も珍しい。多様な作品に自己を登場させた短編集『放屁抄』があり、自選作は川端康成賞を得た『伯父の墓地』と『夕陽の河岸』。「50代に入つた頃から…同族の人たちの眠むる墓に、或る親しみを覚えるようになった」と伯父との過日を懐かしく追想し、伯父の死を聞いた翌々年、故郷に墓参する。墓地の奥に「土葬」の「伯父の墓石」を見いだすと「穏やかに気分になつてくる」のであった。『夕陽の河岸』は二・二六事件や満州事変、国際連盟脱退の時代を背景に、小学生から大人になるまでの同世代のGとの交遊から死までを淡々と物語っている。
芥川賞受賞の翌年には病気も快癒し、32歳で結婚。作品は社会性を伴うものへと成熟していく。極端な思考を避け、バランスのとれた健康な感性を持ち味とした。
71歳の時に、「私にとって文学とは、小説であれ随筆であれ、いかなる奇想天外の構想よりも、文章のうま味に在るものと思われる」と述懐。「文章のうま味」とは美文調でも、ねちっこさでもない。無駄を省いた素直な表現に魂が入れば、魅せられないはずはない、というのだ。
代表作の一つ『海辺の光景』は野間文芸賞を受けた自伝的中編。作家の創作のモチーフが網羅され、人生の形成期に体験した母チカへの複雑な愛の記憶と、父信吉への嫌悪が綴られている。「一人息子である信太郎」に、「老耄性痴呆症」で精神に変調をきたした母が危篤との電報が届く。「高知湾の入江の一隅に小さな岬と島にかこまれた」海の眺望できる病院へ駆けつけ、「鉄格子のはまった」「病室」で、「事務的な」医者や看護人の「ぶつきら棒」で冷淡な視線を浴びながら母を看取る。
「母の顔は、すつかり瘦せおちてゐるうへに、醜くゆがんで、…もとの面影はなかつた」。過去の記憶を振り返りながら、彼の心は陰鬱な思いに占領されてしまう。「両親を田舎において、一人だけ都会でくらす」ことに後ろめたさを感じていたのだ。「不思議なほど夫を嫌ってゐた」母だったが、その母を裏切ったのが自分なのは否定のしようがない。「自己嫌悪」に加え、「父と母との間の暗黙の争ひ」の感情にひきずられ彼自身も父に反発していた。
母に盲愛された自分にとって、「郷里」や母との絆はどんな意味をもつのだろう? 主人公の心象風景が暗く蘇る。母の臨終で「メマイの起こりさうな」信太郎が海辺を歩いていると、「眼の前にひろがる光景にある衝撃をうけて足を止めた。…波もない湖水よりもなだらかな海面に、幾百本ともしれぬ杙(くい)が黒ぐろと、見わたすかぎり眼の前いっぱいに突き立っていたからだ。…歯を立てた櫛のような、墓標のような、杙の列をながめながら彼は、たしかに一つの死が自分の手の中に捉えられたのをみた」。
己の行くべきところは、母でも父でもなく、結局、自己の孤独な世界でしかないことを自覚した瞬間であった。平野は「『海辺の光景』は安岡章太郎における青春文学との決定的な訣別を意味している」と結論付けた。
カトリック信徒に
2年後、安岡の情感と理性と批判精神がマッチし、ベストセラーになったのが『アメリカ感情旅行』。ロックフェラー財団の招きで安岡夫婦がアメリカ各地を半年間旅した紀行文で、新安保条約調印や全学連のデモ騒動から、ケネディ大統領の就任式までが書かれている。同時期、フルブライト奨学生として単身アメリカや世界各国を放浪した小田実が出したのが『何でも見てやろう』である。
安岡は、旅先での人々との出会いや出来事に、自分の感想や考えを率直に記した。テネシー州では、ナッシュヴイルやメンフィス、ブランウンズヴィルなどの「暗黒面をさぐってみよう」と、「アメリカ人のコミュニティーを観察」する。黒人教会も含め「教会まわりを」し、献金盆にまごつきながら町になじもうとするが、食前の祈りの作法に「戸惑いや気マズさ」を覚える。異国で「異教徒」扱いされた安岡が、その6年後、遠藤周作の導きでカトリック信徒になるのだから、人生は不思議である。『流離譚』では明治初頭、キリスト信徒の親族の死が描写され、井上洋治神父とは『我らなぜキリスト教徒となりし乎』の共著がある。
ナッシュヴィルに向けニューヨークを発ったのが11月30日。空港で黒人の運転するタクシーに白人と相乗りをすると、「人種偏見」の「小事件」に遭遇。区分けされた「白人と黒人の居住区」や南部と北部の生活意識の差など、アメリカ社会で体験する実際を日本人の視点で考え論じていく。
南部の名門校ヴァンダービルト大学の留学生になった夫妻は、教授に招待されセルフサービスの「無機質の合成化合物みたいな」食事にありつく。「苦手の」パーティーでの失敗談。初めて訪れた家で、婦人にいきなり「ここで泊まって行くように」と言われ、あけっぴろげな親切心と家族のような親密さで「ショウ」「ミチュ」と呼ばれ圧倒される。近代的な「スーパー・マーケット」での買い物や、「ソーセージをパンにはさんだホット・ドッグ」と「コカコラ」が「ピクニックの御馳走」。「ドライヴ・イン・シアターを眺めたときの奇怪な印象」を記載。
やがて「教授やクリスチャンや優等生や博士の卵」など「まともな人たちに出会いすぎた」と自嘲する。もっと職業や生き方の違う人間たちと「生活してみたい」「その方が…ずっと自分に似つかわしいアメリカを学べるにちがいない」と考えるが、紹介された人から原爆投下やハガチー事件、朝鮮半島のこみいった政治問題を聞かれ、「ドク気をぬかれたまま」「口ごもる」のであった。
さらに奥地の、読み書きができず選挙権のない黒人たちを訪ねる。著者の心象に形を変えながら刻まれた記憶は、アメリカで「一番厄介な問題」とみなされている「人種差別」であり、「黒人問題はすなわち白人の問題である」と明察する。
その後、安岡はアレックス・ヘイリーの『ルーツ』の共訳をしたり、大学紛争と反戦運動のナッシュヴィルへの内省的訪問記『わがアルト・ハイデルベルヒ』を出版している。
日本文学大賞
1981年に長篇『流離譚』で日本文学大賞を受賞。流離には生まれ故郷を離れ、異郷の地をさまよう意味があり、本作は「私の親戚に一件だけ東北弁の家がある」から始まり、自身のルーツを忠実に探索している。
安岡の先祖は父方・母方とも土佐の郷士。日中戦争が拡大していた頃、30年来音信のなかった「奥州の安岡正光」を名乗る親戚が、東京の安岡家を訪ねてきた。なぜ別系が福島県の郡山近くに住むようになったのか、安岡は不思議に思い、探究する。
同作を「本卦がえり」と評したのが国文学者の保昌正夫で、安岡が慶応予科の時代に書いた短編時代小説『首斬り話』を挙げる。安岡も『海辺の光景』の後に、父の家を遡って見たいと思っていたという。出発点から「資質の鉱脈を掘り当てていた作家」だと推察したのは評論家の勝又浩。これまで眠っていた稟質が、タイムリーな年齢・時期・心境に合致し覚醒したというのである。
土佐の自由民権運動の発祥地の歴史を生きた3兄弟を軸に、「幕末、維新、民権運動」の激動史をひもとく。膨大な史料や文献、日記や手紙などを前に、作家としての眼力や感触をもって血なまぐさい「歴史の裏面」に斬り込んでいく。
上巻の主役は安岡家の次男・嘉助で、天誅組の蜂起に加わり、吉田東洋を暗殺し脱藩、京都の獄舎で打ち首にされる。下巻の主人公は土佐勤王党にかかわって入牢した兄の學之介で、討幕軍とともに戊辰戦争に従軍し会津で討死にした。その遺児が福島県に移住したのだ。三男の道之助は自由民権の活動家になる。小林秀雄は「歴史小説の新手法があると見てもよいのでは」と評した。
安岡は芥川賞選考委員を51歳から15年間、大佛次郎賞や伊藤整文学賞の選考委員も務め、1976年に日本芸術院会員となる。歳を重ねながら感性を豊かにし、幾星霜の辛酸を経て温厚な笑顔になった。92歳で永眠し、カトリック教会で追悼ミサが執り行われた。(2023年10月10日付 804号)