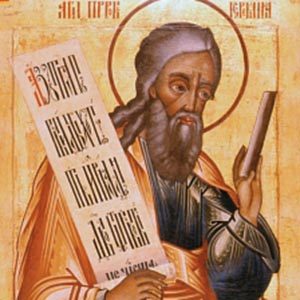最澄と徳一の「諍論」と日本仏教
2022年2月10日付 784号
昨年から今年にかけて、伝教大師1200年大遠忌記念特別展「最澄と天台宗のすべて」が東京・九州・京都で開かれ、改めて最澄が開いた天台宗・比叡山延暦寺への関心が高まっている。比叡山は「日本仏教の母山」と呼ばれるように、鎌倉仏教の宗祖たちがここで学び、山を下りて、大衆に仏教を広めた。
最澄の生涯で興味深いのは法相宗の徳一との間で繰り広げた「三一権実諍論」である。
徳一の事績は、福島県磐梯町にある国指定史跡慧日寺跡にその一端を見ることができる。奈良を離れた徳一は東北に布教し、平安時代の初め「仏都会津」と呼ばれるほどの興隆を当地にもたらした。その足跡は、やはり東北に教線を広げた最澄と似ている。
仏性論をめぐり
徳一の足跡は、鎌倉幕府打倒の計画が漏れ、後醍醐天皇が三種の神器を保持して挙兵した笠置山にもある。京都の南端、奈良との県境にある笠置山は修験道の行場で、その拠点が笠置寺。徳一は、権力に近づき堕落した興福寺を離れ、ここで修行し、その後、東北を目指したのである。その足跡は、東大寺で具足戒を受けながら、19歳で比叡山に籠った最澄と、これも似ている。
最澄が唐への留学を思い立ったのは、日本に招来された大量の仏典を研究する中で、南都六宗の背景にある天台教義の真髄を学ぶ必要を感じたからとされるが、もっと切実な問題として、天皇が何度も和解の詔を出すほど深刻な三論宗と法相宗の対立があったという。
三論宗は龍樹の『中論』、法相宗は無着・世親兄弟の唯識思想を旨とし、両学派の論争は「空有(くうう)の論争」とよばれ、中国、インドにまでさかのぼる、仏教の本質にかかわっていた。中心は仏性論争であり、三論宗が「一切衆生悉有仏性」説なのに対して、法相宗は人間には生まれながらの違いがあり、成仏できない人もいるとしたのである。
これを解決するには、隋の智顗が開いた天台宗を学び、招来するしかないと考えた最澄は、親交のあった和気氏を通じ、桓武天皇に唐への留学を願い出たとされる。天台宗は天台法華宗とも呼ばれるように、釈迦の最後の教えとされる法華経に基づく大乗仏教の宗派である。桓武天皇に近い和気氏から最澄に働きかけたとの説もあり、切迫した事態が背景にあったことがうかがえる。仏教立国を目指した日本の本質的な危機と言えよう。
今から考えると、両論の違いは釈迦の教えが多岐にわたり、目の前にいる悩める人に語った言葉が基になっているからである。死ぬしかないというほどの絶望的な人には、浄土教のように、死後の救いを語ったのであろう。自分の思想より、相手の心の救いを優先していたのである。多様な人間を対象にしたので、教えも多様にならざるを得ない。さらに、それを聞いた弟子たちの解釈も多様であった。
日本仏教にとっての「諍論」の意味は、論争そのものにあったと言えよう。論争により概念が明確になり、言葉が研ぎ澄まされ、思想が深まるからである。いわゆる論理学も仏教に含まれてもたらされたのであり、論争を繰り返しながら、仏教は日本的風土に土着していったのである。
徳一と最澄、さらに空海の足跡を比較し、「諍論」よりも重要に思われるのは、山での修行である。最澄が12年間、比叡山に籠ったように、空海も大学を離れ、山で修行に励んでいる。彼らだけでなく、当時の学僧にとって山での学びは当たり前のことだったという。
山は古来、日本人が信仰を育んできた場所であり、死者を葬ってきた先祖たちの住まいであった。それが、当時の人たちにとって神々と共にある空間だったのである。
コロナとの共生
コロナ禍は第六波がかつてない拡大を示し、いまだ収束の兆しが見えない。生物に寄生して繁殖するウイルスには、生物のような「死」はない。死が生まれたのは、生物が有性生殖をするようになってからで、進化の結果というのが生物学の見解である。この生物学の死生観は、自然に帰るという日本的仏教の死生観に通じている。
その意味で、コロナ禍は、自然との付き合い方の再考を、私たちに迫っているのではないか。自然から生まれたから、自然に帰るという、ごく自然な死生観を共有することが、コロナとの共生をもたらすのかもしれない。